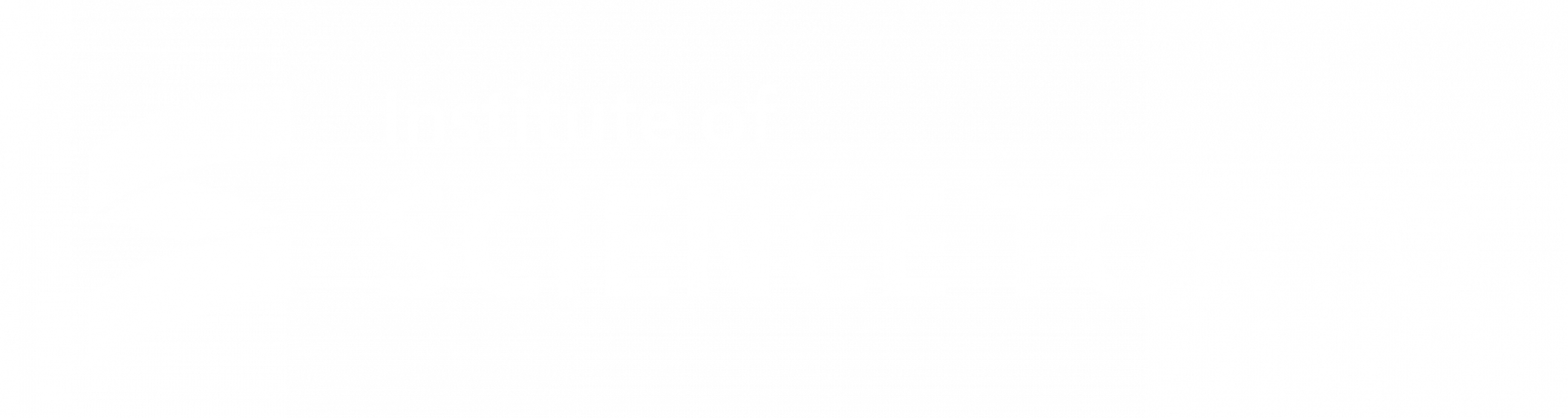研究生活・その先
1.研究活動の日常
研究室の設備
バーチャルラボツアー(研究設備編)(準備中)
実験に必要な設備は、基本的に同じフロアにあるJ3-1121室に集約されています。ここでは以下のような作業が可能です:
• 合金溶解・熱処理・切断・研磨・電子顕微鏡試料作製
• X線回折、熱分析、熱機械分析
• 力学試験、硬さ試験

また、各種電子顕微鏡や圧延装置は、細田・田原研究室と共用しています。研究に必要な設備は完備しています。
進捗会
毎週水曜日9:30からオンラインで進捗会を行っています.研究データのディスカッションが中心ですが、それ以上に大切なのは、研究上・生活上の悩みを共有し、早めに解決の糸口を見つけることです。発表する内容がない週もあるかもしれません。それでも構いません。参加すること自体がチームの一員としての大切な時間です。

輪講(雑誌会)
輪講では、専門知識の習得、英語文献の読解、発表力の向上を目的としています。
質疑応答の時間では、他のメンバーの視点から新たな気づきを得ることも多く、理解を深める貴重な機会です。各クォーターに1回(15分)の発表を行います。
学会発表・修論発表・就職活動のプレゼンにもつながる、実践的な力が身につきます。

研究指導・サポート体制
稲邑教授と松村助教が、学生一人ひとりの適性に応じて丁寧に指導します。
研究に必要な基礎理論については、稲邑教授が第1クォーターに講義します。学部の線型代数の初歩的知識があれば誰でも理解できます。
研究室全体で共通の知識を共有しているため、理論の理解からコーディングの方法まで、先輩が親身に教えてくれます。
新入生には、先輩の研究テーマと関連するテーマが与えられるため、安心してスタートできます。
学会発表
成果が出たら、国内学会,国際会議に参加します。世界に向けた第一歩をしっかりサポートします。
輪講や日々のディスカッションを通じて鍛えたプレゼン力を活かし、研究成果を発信します。
▶️ 学生の受賞歴はこちら
▶️ 国際会議での成果発表はこちら
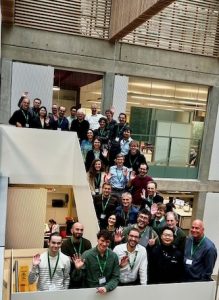
2.研究室での生活
稲邑研学生の主な出身大学(過去8年)
さまざまな大学から学生が集まっています!
•東京科学大(東工大),横浜国大,茨城大,金沢大,九州大
•北里大,明治大,日本大,東京理科大,東海大,芝浦工大
•八戸高専,富山高専,
•大連理工大,中国石油大学(北京),École Nationale des Ponts et Chaussées
学生室の環境
バーチャルラボツアー(学生室編)(準備中)
学生全員が、J3棟1114室にそれぞれ専用の机とPCを支給されて配置されています。
この部屋には松村助教が常駐しており、稲邑教授も同じフロアにいるため、日常のちょっとしたやりとりから研究の相談まで、安心して取り組める環境が整っています。
コアタイムについて
稲邑研究室では、特定のコアタイムは設けていません。活動の時間帯は、なるべく教員の勤務時間に重なるようにお願いしています。そのほうが相談やサポートもしやすくなります。なお、夜間に薬品を使う実験や、圧延・火気を伴う作業は、安全の観点から禁止しています。
季節イベント
研究に集中する一方で、研究室内での交流やリフレッシュの機会も大切にしています。
以下のようなイベントを毎年行っており、他研究室との交流も積極的に行っています。
こうした時間も、研究生活の大切な一部です。
• 新入生歓迎会(4月)
• 就職活動お疲れ様会
• 忘年会
• 追いコン(卒業生送別会)
• 研究室旅行(細田・田原研、曽根・Chang研、大井研との合同)

3.進路・就職
就職活動
東京科学大学・物質理工学院材料系の学生であれば、どの研究室を選んでも、就職活動においては同じスタートラインに立つことができます。
稲邑教授自身も、進路や就職について親身に相談にのりますが、必要以上に干渉はしません。
インターンや志望企業の選定は、自分自身で考えて決断することが大切だと考えています。
稲邑研の卒業生は、製造業・IT・官公庁・研究機関など幅広い分野で活躍しています。
以下は主な就職先の一部です。(博)は博士課程修了生の就職先です。
• 日本製鉄(博)、JFEスチール、神戸製鋼、三菱マテリアル、日本冶金、三菱重工、SUBARU、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業
• 経済産業省、東京都庁、新エネルギー・産業技術総合開発機構(博)
• NTT、キオクシア、大日本印刷、TDK、武蔵エンジニアリング
• 丸紅、博報堂、リクルート、野村総合研究所
• 東京科学大学・助教(博)、神戸大学・助教(博)
博士課程を考える人へ
研究者として仕事がしたいと考えているなら、博士課程への進学を強く勧めます。
博士号は、単なる学位ではなく、国際的に通用する“研究の免許証”のような意味合いも持っています。

いまは、経済的支援制度も整備されており、安心して博士課程に挑戦できる環境が整っています。
稲邑研の博士課程学生は全員,授業料以上の経済的支援を受けることができています。
博士課程学生への支援